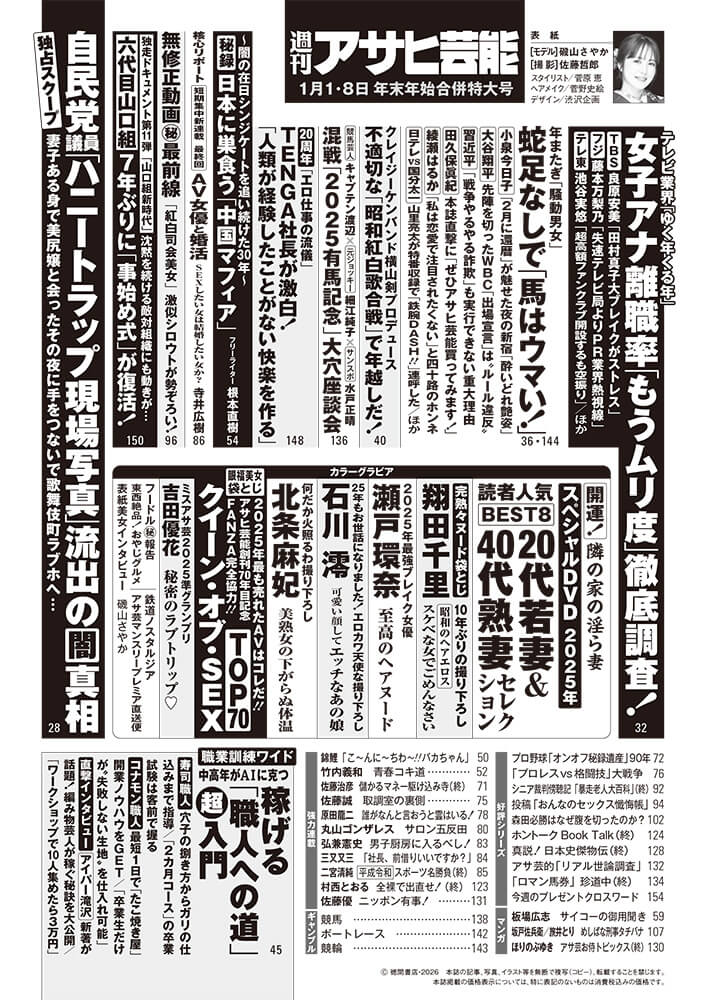記録的猛暑に見舞われる今夏、エアコン室外機の「耐熱性能」が改めて注目されている。特に話題を集めたのが、ダイキンが展開する「外気温50℃まで耐えられる室外機」だ。一部機種(Dシリーズ)には、カタログに「高外気タフネス冷房(外気温50℃対応)」...
記事全文を読む→【考古学ミステリー】ミシガン湖底に沈む1万年前のストーンヘンジに「怪物マストドン」の岩絵が!
中心部に配置された15の巨石と、その外側に立てられた、門を思わせる巨石。これがいったいどこから運ばれてきたのかが、長年謎とされてきた。イングランド南部ウィルトシャーにある、ストーンヘンジである。
近年の研究で、この巨石がウィルトシャーから北に約25キロ離れたマールバラ付近のものであると特定されたが、その運搬方法はいまだ定まっていない。なにしろストーンヘンジ周辺には川がないため、切り出した石の下に丸太を敷いて川まで運び、船などに乗せて運んだという説には、いまひとつ説得力がない。それが今も謎に包まれている理由なのだ。
そのストーンヘンジがアメリカ五大湖のひとつである、ミシガン湖の湖底で発見され、考古学者らの間で大きな話題になったことがある。2009年のことだった。考古学研究者が語る。
「発見したのは、ノースウェスタンミシガン大学の水中考古学研究チーム。彼らが湖に沈んだ難破船調査のためソナーを使用していたところ、水深12メートル付近で円を描くように配置された環状列石、つまりストーンサークルを発見したのです。その形状が、イングランドのストーンヘンジそっくりだった」
このストーンヘンジには不思議な絵が描かれており、なんとそれが4000万年前から1万年前に生息していたとされる「マストドン」という生物の姿に酷似しているのだ。
「マストドンらしき絵が描かれた俵型の丸石は長さ1.5メートル、高さ1.2メートル。マストドンは象やマンモスに近い哺乳類で、別名『シノニム』と呼ばれ、怪物レヴィアタンがその由来です。ヨーロッパ大陸やアジア大陸、アフリカ大陸など幅広い場所で、中新世(2400万年前から510万年前)から更新世(258万年前から1万7000年前)にかけて生息していた。仮に1万年前まで生き残っていたとすれば、そのペトログリフ(岩絵)は人類が彫った可能性が高い。古代期、まだミシガン湖の一部は水に浸かっていなかった場所もあるとされることから、発見されたストーンヘンジとマストドンの絵は、この時期に形成された可能性があります」
むろん誰がどんな目的でストーンヘンジを作り、そこにマストドンを描いたのかはわからないながら、世界では5番目の面積の淡水湖の湖底に、1万年前の遺跡が静かに眠っていたとは…。水中考古学者らの間からは「まだ何か眠っているはずだ」という期待の声が上がったのも当然かもしれない。
「ミシガン」とはオジブウェー語(アメリカ先住民の言語)で「偉大な水」を意味する。偉大な水をたたえたこの湖に眠る、ストーンヘンジの謎が解き明かされるのはいつなのか。
(ジョン・ドゥ)
アサ芸チョイス
胃の調子が悪い─。食べすぎや飲みすぎ、ストレス、ウイルス感染など様々な原因が考えられるが、季節も大きく関係している。春は、朝から昼、昼から夜と1日の中の寒暖差が大きく変動するため胃腸の働きをコントロールしている自律神経のバランスが乱れやすく...
記事全文を読む→気候の変化が激しいこの時期は、「めまい」を発症しやすくなる。寒暖差だけでなく新年度で環境が変わったことにより、ストレスが増して、自律神経のバランスが乱れ、血管が収縮し、脳の血流が悪くなり、めまいを生じてしまうのだ。めまいは「目の前の景色がぐ...
記事全文を読む→急激な気温上昇で体がだるい、何となく気持ちが落ち込む─。もしかしたら「夏ウツ」かもしれない。ウツは季節を問わず1年を通して発症する。冬や春に発症する場合、過眠や過食を伴うことが多いが、夏ウツは不眠や食欲減退が現れることが特徴だ。加えて、不安...
記事全文を読む→