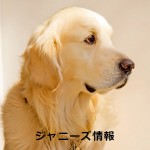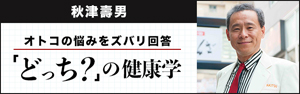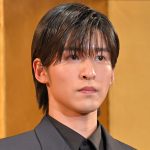JR東日本が山手線などの切符の初乗り料金を10円値上げする申請を、国に対して行う見通しであることが明らかになった。
値上げが実施されるのは2026年3月。普通運賃だけでなく、通勤や通学の定期券も対象となる。山手線の普通運賃であれば、初乗りは150円から160円へとアップする。
山手線は乗車人員ランキングのトップ10に、7つの駅が入る。利用者の多い路線だけに、影響は大きそうだ。
山手線は都内をぐるっと一周する「環状線」として知られるが、正確には環状線ではない。正式路線名としての山手線は、品川駅を起点に渋谷駅、新宿駅、高田馬場駅、池袋駅などを経由して、田端駅までとなっている。環状線ではなく、アルファベットのCのような路線なのである。
では田端駅から品川駅は何なのかといえば、田端駅から東京駅までは東北本線、東京駅から品川駅までは東海道本線を経由している、という扱いになっている。
もっとも、これは正式路線名においてのことで、運転系統としての「山手線」は、一般的に知られている環状線になる。
なぜこのようなことになったのか。理由は山手線の成り立ちあると、鉄道ジャーナリストは言う。
「山手線は最初から環状線として計画されたのではなく、様々な路線を繋いでひとつにしたからです。日本初の鉄道は1872年にできた品川駅と横浜駅間ですが、新橋駅と品川駅の間が山手線になります。1883年に上野駅と熊谷駅を結ぶ路線が開通し、この上野駅と田端駅の間も加わります。1885年には品川駅から新宿駅を通って赤羽駅へ続く品川線が開業し、品川駅と池袋駅の区間も加わりました。以降は1903年に池袋駅と田端駅の間が開通し、1910年に新橋駅と東京駅、1919年に東京駅から神田駅まで延伸され、1925年に上野駅と神田駅が開通して、やっと環状線になりました」
正式路線名としての山手線の起点は品川駅で、終点は田端駅だが、運転系統としての起点は異なる。外回りが池袋駅で、内回りは大崎駅だ。
何度も利用している山手線には、こんな秘密が隠されているのだった。
(海野久泰)