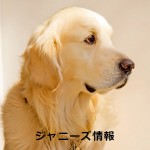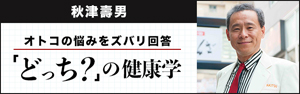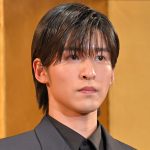その映画の物語は、第二次世界大戦中の太平洋を舞台に、繰り広げられる。上官に反抗した罪で軍法会議にかけられる日本兵と、イギリス人捕虜を乗せた輸送船が、連合軍の攻撃を受けて沈没。無人島に取り残された2人がそこで未知なる獰猛生物に襲われ、敵味方だったものの、生き延びるために化け物に立ち向かっていく、というものだ。
これは2024年10月、東京国際映画祭で公開された、ディーン・フジオカ主役のインドネシア、シンガポール、イギリス、日本の四カ国合作ホラー映画「オラン・イカン」だ。
「オラン・イカン」というのは、インドネシアで伝承されてきた民話に登場する、上半身は人間、下半身は魚という「半魚人」。インドネシア語でオラン=人間、イカン=魚を意味する。ちなみにインドネシアではほかにも、猿人タイプの大型UMA「オラン・ガダン」、小型のUMA「オラン・ペンデク」などが生息しているといわれる。
そんなインドネシアの島々は、第二次世界大戦での激戦地が多かった。そのため、食料確保に汲々としていた兵士らは生き抜くため、それこそ何でも口にした。コウモリやオオトカゲ、さらに真意のほどは不明ながら、奇妙な半魚人、つまり「オラン・イカン」も殺して食料にしていた、との奇談が残されている。
終戦間近の1945年、インドネシア東部のアラフラ海に浮かぶケイ諸島には、数千人の日本兵が駐留。皆が食糧難にあえいでいたといわれる。
そんなある日のこと。現地住民が海岸に打ち上げられた、人間のような上半身で腰から下にはウロコが付いた生物の死骸を運んできた。尾ビレを持ち、黒光りする1メートルほどの大きさだった。
「死骸には貝殻や藻がびっしりとへばりついていたが、兵士らは餓死寸前。衛生兵が死骸を切り分け、これを焼いて食べたといわれています」(未知の生物を取材するジャーナリスト)
実はこの島には時々、イルカやクジラなどの哺乳類が迷い込むものの、高い水温に耐えきれず息絶えてしまうことが多かったという。そのため、兵士たちが食したのは「人魚」と称されるジュゴンだったのではないか、との説がある。この話が復員兵により広がり、次第に尾ヒレがついて伝説となったのでは、と…。
このままいけば餓死するとわかっていたならば、何でも食べるはずだ。そんな状況下、目の前に半魚人の死骸があったら…。想像しただけで身震いするが、それが戦争という現実であることも忘れてはならない。
(ジョン・ドゥ)