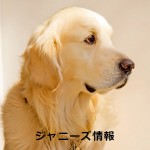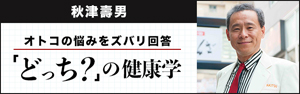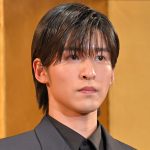昨今はどこもかしこもデカ盛りブームで、そんな店には行列ができる。ギャル曽根のような大食いタレントが連日のようにテレビ番組に出演するが、江戸時代後期にはすでに「フードファイターの元祖」のような人物が実在した、との記録が残っている。
その人物は大貫善兵衛といい、「南総里見八犬伝」で有名な滝沢馬琴を中心とした文人サークル「兎園会」が編集した江戸時代の随筆集「兎園小説」に登場する。喜田川守貞が江戸時代の風俗を記録した資料「守貞漫稿」にも、それらしき人物が描かれている
主な記録として残っているのは、一度の食事で白米3升(約4.5キロ)に加え、うどん30人前、さらに餅100個を平らげたというものだ。うどんは通常1人前が200グラムだから、6キロにもなる。切り餅1個は50グラムで計算すると、5キロ。つまり善兵衛は一度に炭水化物15キロ以上も食べていたことになる。
大相撲史上に名を残している雷電為右衛門は197センチ、169キロで、一度の食事で米1升を平らげ、力士仲間から「雷電の食いっぷりは別格」と呼ばれていたが、善兵右衛門はさらにその上をいく。大食いファイターとして有名だったジャイアント白田は、一度にラーメン15杯、もしくはそば10キロを食べたが、善兵衛の記録には及ばない。まさに化け物のような胃袋を持った人間が、善兵衛だった。
当然、その異常なまでの食欲は江戸庶民の間で知れ渡り、見世物小屋に出演することもあったという。米5キロが3500円にもなる今とは違うとはいえ、当時としても、いくら稼いでも食費がが足りなかったという。エンゲル係数が100を超え、最後は破産に追い込まれたと伝わっている。
もっとも、あの武蔵坊弁慶は、一度に米一俵を平らげたというが…。
(道嶋慶)