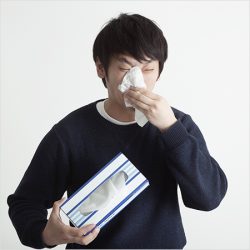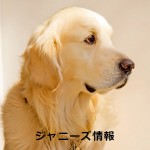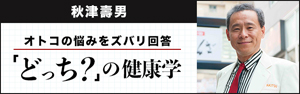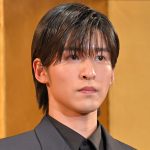今や日本では滅多に名前を聞かなくなった寄生虫。体内に虫がいると聞いただけで卒倒者が続出しそうなご時世だが、これがなんとアレルギー性の体質を改善するという。
戦後の日本では、60%前後の人に回虫(寄生虫のひとつ)がいた。その後衛生的な環境の広がりにより激減したが、人間に寄生する寄生虫は、世界では約200種類と報告されており、種類によっては死に至るものまでいる。しかし、中には“良い寄生虫”もいるという。この“良い寄生虫”を体内で飼育することで体質改善ができ、アレルギー性の体質が改善され健康になるというのだ。そう唱えているのは寄生虫の研究44年になる藤田紘一郎東京医科歯科大学名誉教授だ。自身の著によれば、みずからの腸内で15年間6代にわたり条虫(サナダムシ)を飼育していたという筋金入りなのだ。先生の著にはこうある。
〈汚物の流れる川で水遊びする。その水で炊事、洗濯をする。調べたらほとんどの人に回虫が見つかった。しかし、そんな子供たちの肌はつやつやとしている上にアトピー性皮膚炎や花粉症、気管支ぜんそくなどのアレルギー疾患の人はいなかった〉
そして、社会が清潔になるにつれ寄生虫は減ったが、アレルギー性の患者は急増した。そこで藤田氏は寄生虫の研究を始める。1977年には「回虫が消えたからアレルギー疾患が増えた」という論文も書いている。藤田氏はサナダムシ飼育の経験をこうも言っている。
「花粉症にもならず、中性脂肪もコレステロールも大幅に落ち、至って健康になった。回虫は有史以前から人と共生してきた。宿主が元気でいっぱい食べてくれないと困るわけで、宿主をアレルギーにもガンにもなりにくい体質に変化させてくれる」
ネットではいろいろなサナダムシが販売されており、これをカプセルに入れて飲んでいる人もいるようだがサナダムシと言われている寄生虫は約3000種類以上いるとも言われており、人に害を及ぼすものも数多いともいうから単純に真似をするのは危険だが、藤田氏は超清潔志向に警鐘をならしてもいるのだ。
「殺菌・抗菌・除菌・防臭グッズのコマーシャルが溢れ、無菌状態で生活し、人間本来の免疫力をどんどん弱めている。“清潔病”は身体の抵抗力を弱めるばかりでなく、人間としての感性まで萎縮させ、日本人の“生きる力”までも衰弱させてしまう。人間が生き物である、という認識が薄れている」
寄生虫の体内飼育は無理だが、真の健康を考えるヒントはありそうだ。
(谷川渓)