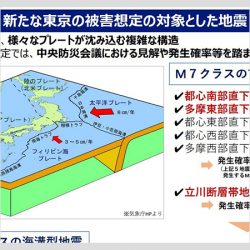当連載では都合21回にわたって都防災会議による新被害想定の大ウソを暴いてきたが、本編の締め括りとして、その舞台裏で秘かに囁かれ続けてきた「カタストロフ待望論」について記しておきたい。
「カタストロフ」とは「破滅」「破局」「終末」などを意味するフランス語だが、この場合は「大地震がもたらす壊滅的な状況」を指している。そのような全滅状態が「待望」されているとは、いったいどういうことなのか。都の元都市整備局幹部が明かす。
「例えば、木密地域(木造住宅密集地域)を解消するといっても、そもそも全面的かつ一斉的な街の再整備など不可能です。同様に、ビルの耐震補強や建て替えも、事実上、部分的にしか進みません。つまり『大地震が来れば、問題のある地域は全滅する。全滅してからの方が、むしろ再整備はやりやすい──』。これがカタストロフ待望論者の偽らざるホンネです。実際、この手の待望論は『都市計画屋』を中心に根強く囁かれてきました」
中には、「街が焼け野原になったり、瓦礫の山になったりした時こそ、オレたちの出番だ!」と息巻いている都市計画屋も少なくないというからアキレ返る。都の元総務局総合防災部幹部も次のように指摘しているのだ。
「都の震災対策が中途半端なものであり続けている背景にも、カタストロフ待望論が横たわっています。どうせ全滅してしまう地域にカネをつぎ込んでもムダになる。だからといって、何もやらないというわけにもいかない──。実際、このように考える防災担当者は少なくありません。10年ぶりに見直された今回の新被害想定にしても『何もやっていないわけではない』ということを正当化するために、地震対策の過大評価と被害想定の過小評価が強調されるに至ったのではないかと、私はみています」
結局、都の防災会議の面々にとっても、「カタストロフ」は織り込み済みの出来事、すなわち「想定内」の出来事だった、のである。
次回からは本編に続く「番外編」として、「大地震が虎の子の資産(戸建てやマンションなどのマイホーム)にもたらすリスク」を数回にわたり紹介していきたい。
(森省歩)
ジャーナリスト、ノンフィクション作家。1961年、北海道生まれ。慶應義塾大学文学部卒。出版社勤務後、1992年に独立。月刊誌や週刊誌を中心に政治、経済、社会など幅広いテーマで記事を発表しているが、2012年の大腸ガン手術後は、医療記事も精力的に手がけている。著書は「田中角栄に消えた闇ガネ」(講談社)、「鳩山由紀夫と鳩山家四代」(中公新書ラクレ)、「ドキュメント自殺」(KKベストセラーズ)など。