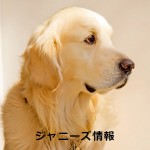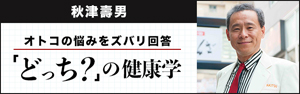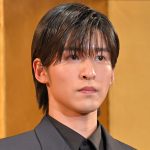熊本県とJR九州が、肥薩線を2022年度に運転を再開させることで合意したと発表した。
肥薩線は2020年7月の豪雨の影響で、八代駅から吉松駅間が不通になっているが、八代~人吉の52キロを2033年度までに復旧させる。この間には14の駅があったが、そのうちの11駅を復旧させる予定だ。瀬戸石駅、海路駅、那良口駅の3つは復旧を見送り、廃止される見通しとなっている。復旧後は県と沿線自治体が鉄道施設を所有し、JR九州が運行を行う「上下分離方式」が採用されるという。
上下分離方式にすることで、どんなメリットがあるのか。鉄道ジャーナリストの解説を聞こう。
「鉄道インフラと運行を別にすることで、運行の負担を軽くすることができます。肥薩線であれば、これまではJR九州が鉄道インフラも車両メンテナンスも運行も行ってきましたが、上下分離方式に移行後は、車両のメンテナンスと運行だけに専念できます」
このメリットは大きく、他の鉄道路線でも採用されている。鉄道ジャーナリストが続けて言う。
「2011年の豪雨で一部区間が不通になったJR東日本の只見線は、復旧時には上下分離方式となりました。南阿蘇鉄道も熊本地震の被害から復旧した2023年に、上下分離方式に移行しています。2022年の豪雨で一部区間が不通になっている山形県の米坂線も、上下分離方式での復旧が検討されている。簡単に言えば、沿線自治体が復旧費用の多くを負担し、復旧後の施設維持費用も持つのでなんとか廃線にしないでほしいと鉄道会社にお願いした、ということです」
今後も上下分離方式の路線は増えていくことだろう。
(海野久泰)