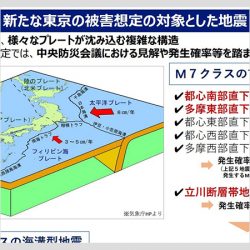前回指摘した「医療機能マヒ」と同様、発災直後から直面することになる「遺体処理問題」についても、新被害想定での言及はわずか1ページに留まっている。
そこで思い出されるのが、85年に起きた日本航空123便墜落事故で、救助活動や遺体収容などの指揮を執った、群馬県上野村の黒澤丈夫村長が筆者に語った言葉である。
当初、墜落現場となった御巣鷹の尾根に近い上野村では、村の消防団員らによる懸命の救助活動が行われた。その後、活動の主体は遺体の捜索と収容へと移っていったが、村外から派遣された自衛隊なども含めて、捜索隊員らは数日をかけて遺体捜索に苦闘しては下山し、村の体育館で休息を取ってはまた捜索に向かう、という過酷な日々を強いられた。
言うまでもなく、捜索現場は凄惨を極めた。気温の高い真夏の山中での捜索、それも昼夜を徹しての辛い捜索である。さらに言えば、五体が整った遺体はむしろ少なく、多くの遺体には表皮の剥脱、内臓の破裂や脱出、全身の挫滅や挫折などが見られ、かつ、それらの遺体の多くが焼損を受けて黒焦げになっていたのである。
筆者が上野村役場に黒澤村長を訪ねたのは事故から12年後のことだったが、時に目に涙を滲ませ、時に声を震わせながら当時を振り返った黒澤村長は、それまでの話をいったん区切るや、次のように「静かな怒り」を口にしたのだ。
「消防団員も役場の職員も心身ともに限界に追い込まれていく中、ある時、捜索隊員らの昼食に鶏肉の照り焼き弁当が配られたのです。弁当は日航の『現場責任者』が手配したものでしたが、弁当のフタを開けた途端、隊員らは前日までに目撃していた凄惨な事故現場を思い出し、中には照り焼きの匂いに耐え切れず嘔吐してしまう者もいました。日航の現場責任者は本当の現場を知らず、凄惨な現場に対する想像力も欠如していたのです。この時ばかりは、私も語気を強めて抗議しました」
翻って今回の新被害想定における遺体処理問題の記述を見ると、同様の意識のズレ、同様の想像力の欠如が顕著なのである。その詳細については次回に譲るが、この際、都の防災会議は、11年にこの世を去った黒澤村長の言葉を、改めて肝に銘ずべきだろう。
(森省歩)
ジャーナリスト、ノンフィクション作家。1961年、北海道生まれ。慶應義塾大学文学部卒。出版社勤務後、1992年に独立。月刊誌や週刊誌を中心に政治、経済、社会など幅広いテーマで記事を発表しているが、2012年の大腸ガン手術後は、医療記事も精力的に手がけている。著書は「田中角栄に消えた闇ガネ」(講談社)、「鳩山由紀夫と鳩山家四代」(中公新書ラクレ)、「ドキュメント自殺」(KKベストセラーズ)など。