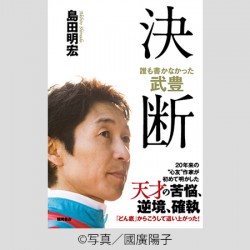武豊騎手と20年来の“心友”である作家・島田明宏氏が書き下ろした「誰も書かなかった 武豊 決断」が大反響を得ている。本書には数多くの「心の葛藤」が描かれているのだが、ダービーもその一つ。昨年、キズナで5度目の栄冠に輝いたものの、そこに至るまでは天才がゆえの苦悩もあった。
武豊は、ダービーに対する強い思いを、騎手になるずっと前から持ち続けていた。先日上梓した「誰も書かなかった 武豊 決断」でも、彼がダービーを制するまでのプロセスに1章を割いている。
父・邦彦がロングエースで1972年のダービーを勝ったとき、彼は3歳だった。あとから話を聞いたり、写真や映像を見て肉付けされたのかもしれないが、父が喜んでいた姿を、ぼんやりと覚えているような気がするという。
「親父がダービー優勝の賞品として、白いクラウンをもらったことはハッキリと覚えています。ダービーの意味や重みをきちんと理解して見るようになったのは、クライムカイザーが勝った年からですね」
76年のそのダービーが行われたとき、彼は小学2年生だった。父が騎乗したテンポイント(7着)を応援しながらテレビを見ていたという。
「父が武邦彦でなかったら、自分も騎手になっていたかどうかわからない」
そう話している彼は、物心ついたときには自然と騎手になりたいと思うようになっていた。
豊少年にとって、「騎手になりたい」という思いと「ダービーを勝ちたい」という夢は非常に近いものだった。いや、ふたつでひとつの夢だった、と言ってもいい。
彼は、そこから少しずつ「夢のダービー」に近づいていく。
84年、競馬学校騎手課程に入学し、その年、初めてライブでダービーを見た。
87年に騎手デビューし、翌88年、初めてダービーに参戦する。騎乗馬はコスモアンバー。当時はフルゲート24頭で、「何もできないまま」16着に敗れた。
翌89年は、タニノジュニアスで24頭中10着。すでに「天才」と呼ばれていた彼でさえ、このころは、ダービーを勝てるような気がしなかったという。
3度目の参戦となった90年の騎乗馬は、南井克巳の手綱で皐月賞を勝ったハクタイセイだった。2番人気に支持されたが、やや距離が長く、掛かってしまい、5着に終わった。
91年はシンホリスキーでブービーの19着。
92年は、騎乗する予定だった馬が故障したため、スタンドから観戦した。
93年は、自身が騎乗して皐月賞を勝ったナリタタイシンで臨んだ。距離適性もあるし、東京向きの末脚を持った馬だったので、スタートからゴールまで勝利を意識して乗った。
結果は3着だったが、1コーナーで10番手以内につけていないと勝てないという「ダービーポジション」などにとらわれず、強い馬の能力を引き出せば勝負になることがわかった。
94年はフジノマッケンオーで4着、95年はオースミベストで8着。
94年というと、彼がスキーパラダイスで仏ムーランドロンシャン賞を勝ち、日本人騎手初の海外GI制覇を達成した年だ。凱旋門賞とブリーダーズCでの初騎乗も果たした。
「世界のユタカ・タケ」にとっても、日本ダービーのタイトルだけは、まだまだ手の届かない「遠いタイトル」だった。
◆作家 島田明宏