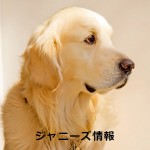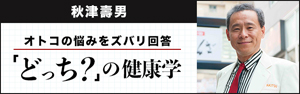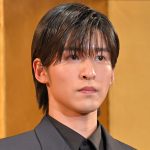源義経の郎党・武蔵坊弁慶は、優秀な土木建築家だった。
奥州平泉で、藤原泰衡軍が放った無数の矢を体に受けて、立ったまま絶命。その最期は「弁慶の立ち往生」として後世に語り継がれている。
遺体は主の義経同様に発見されてはいないが、平泉の中尊寺表参道入り口前の広場には、弁慶の墓と伝わる五輪塔も立っている。
弁慶ゆかりの地は日本全国に散らばっている。だが、注目したいのは、弁慶が作ったとされる橋や、堀ったとされる井戸の存在だ。
治承4年(1180年)の秋、源頼朝は平家討伐のため挙兵した。その際、奥州平泉にいた弁慶は、義経らと鎌倉に駆けつけた。途中、義経主従は現在の小田急線・読売ランド駅近くにある五反田川を渡ることになった。五反田川の川幅は約5メートル。当時、架かっていた橋はひとりが歩いて渡るのがやっとの粗末なもので、馬で渡ることができない。
それを弁慶が、馬も通れる橋に造り直したと伝わっている。新しく作られた橋は丸太を並べ、その上に土を盛ったもので、横からは、さながら「のし餅」を二枚重ねたように見えたという。そのため、二枚橋と呼ばれるようになったという。現在、架かっている橋にはその故事にちなみ、弁慶と義経のレリーフが付けられている(写真)。
当時の馬は、現在のポニーのようなサイズが主流だった。それでも体重は100キロ程度ある。馬の上には甲冑(かっちゅう)に身を包んだ武者がまたがり、橋の上を通行していく。きちんとした知識に基づいた強度計算と土木技術がなければ、橋は架からないだろう。
弁慶は元々、比叡山の僧である。当時、比叡山の僧になるには、国家資格が必要だった。それだけに、比叡山の僧の知識は、当代随一といっていい。弁慶もその持っている知識をフル活用したのだろう。
橋を架けるだけではなく、弁慶は井戸を掘る知識や技術も持っていた。都内には、頼朝に追われた義経一行が落ち延びる際、喉を潤すため、弁慶が掘ったとされる井戸がある。
東大の池之端門脇にある「境稲荷神社」の北側にある「弁慶鏡ケ井戸」がそれだ。一度は埋め戻されたが、再び掘り出され、昭和二十年(1945年)の東京大空襲の際には、焼け出された被災者のライフラインとなったという。
主・義経への忠心と武芸ばかりがクローズアップされる弁慶だが、一級の土木建築家だったことは間違いない。
(道嶋慶)