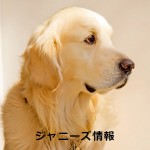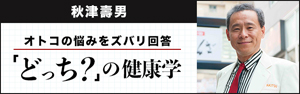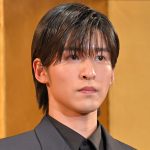男性トラック運転手が安否不明となっている埼玉県八潮市の道路陥没事故から、2週間が経過した。埼玉県の大野元裕知事は2月11日夕、災害対策本部会議の冒頭で、こう言っている。
「見つかったキャビン(運転席)らしきものは、所有する会社車両のものであることが確認された。消防から『中に男性が取り残されている可能性は高い』と聞いている」
だが、捜索活動開始のメドは立っていない。陥没直後は運転手の声が聞こえたのに、救出活動が思うように進まなかったことから一部新聞、テレビでは「初動対応のまずさ」を指摘する声がある。とはいえ、そう簡単にはいかない。
なにしろ陥没現場はさらなる崩落の危険だけでなく、破損した下水道管などの瓦礫が散乱して、視界が悪い。破損した直径4.75メートルの下水道管内は、高濃度の硫化水素が充満する汚水の濁流。埼玉県の復旧工法検討委員会・森田弘昭委員長が報道陣に語ったところによると、
「濁流の流速は(毎秒)1から2メートルくらいはある。人間の力であらがえる流速ではない」
汚水から出る硫化水素は、消防隊員や警察官が下水管に落ちたら即死レベルの高濃度だという。
温泉の源泉周辺で卵の腐った匂いがする、あれが硫化水素で、水分を含むとコンクリートや金属を激しく腐食させる。空気より重いため、低いところに溜まっていく。
このため、陥没事故現場の上流に別の下水道バイパスを作り、破損した下水道管の水流を止めて管内をカラにしたあと、硫化水素ガスを除去。重機を入れて捜索活動にとりかかるまでに数カ月、復旧に年単位を要するというのだ。
国土交通省によると、令和4年度末における、全国の下水道管の総延長は、約49万キロメートル。そのうち耐用年数50年を経過した下水管は全体の7%で、10年後は20%、20年後は全国の下水道管の半数が耐用年数を超える。
とりわけ陥没現場のように幹線道路の下を通り、下水道処理施設に近い下流、下水道管径が太くて下水流量も多く、かつ軟弱地盤でゴミがたまりやすいカーブ地点は耐用年数に達していなくても、車の往来と硫化水素で下水道管の劣化が激しい。次にどこで同じ事故が起きてもおかしくないのだ。そうこうするうち、千葉県大網白里市でも住宅地の道路が陥没し、上水道管が破裂する事故が起きた。
東京五輪と大阪万博を機に日本全国のインフラ整備が進んだのに、五輪と万博は2巡目に突入しながら、老朽化したインフラはそのまま放置。インフラ維持に必要な土木技師を育成してこなかったので、大規模下水道管交換工事もままならない。日本中に時限爆弾が仕掛けられたように、下水道管の腐食は今日も進んでいる。
(那須優子)