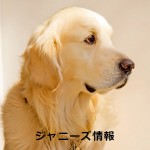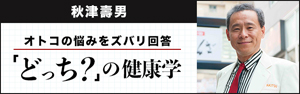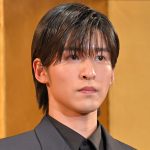3月28日、ミャンマーでマグニチュード7.7の大地震が発生した。4月3日時点で3000人を超える死者が確認されているが、現地の被害状況がまだ把握されておらず、この数字はまだ大幅に増えることが見込まれている。
現地の状況がなかなか把握できないのは、もともと遅れている社会インフラのせいもあるが、ミャンマーがいまだに激しい内戦下にあることも原因だ。冷戦時代から長い間、軍事独裁政権が続いていた同国では、一時期は選挙に基づいた民主的政治が行われたこともあったが、それも実際には最高権力を握る軍部の了解内でのことで、そんな制限的な民主的政府も21年には軍のクーデターで打倒された。以後、同国では軍事政権が独裁的に権力を保持している。
この軍事政権に対し、現在、政府を追われた民主派勢力が武器を持って戦いを挑んでいる。それまでもミャンマーでは各地の少数民族ゲリラが独自の勢力を持っており、軍事政権と戦ってきた歴史があったが、こうした反政府ゲリラの列に民主派勢力が加わったのだ。ミャンマー軍事政権は中国とは良好な関係にあるが、国際社会の多くの国々から非難されている。08年に公開されたシルベスター・スタローン主演の「ランボー/最後の戦場」は当時の軍事政権の残虐さを描いているが、現在も軍事政権の圧政ぶりは同じである。
そんなわけで現軍事政権は、国際社会との関係が悪い。これまで災害は何度もあったが、外国と協力することはほとんどなかった。ところが、今回は政権が早々に海外に協力を要請した。これは異例なことだ。
最初に到着したのは中国の救助チームだったが、その後、シンガポール、マレーシア、インド、ロシア、日本など多くの国がチームを送った。ただし、中国に忖度し、地震災害救助に慣れている台湾の救助隊受け入れは拒否している。また、閉鎖的な軍事独裁国のため、外国メディアへのビザ発給も拒否している。驚かされるのは、軍事政権が地震発生後も、敵対する反政府ゲリラの支配地域の村落への空爆を行っていることだ。国民の安全よりも自らの権力による支配を優先するのが軍事政権なのだ。
そんな軍事政権を率いるのが、ミン・アウン・フライン国軍総司令官である。軍による行政機関である「国家行政評議会」議長、暫定首相、大統領代行を兼任し、文字通りの独裁者となっている。
ミン・アウン・フラインは1956年生まれの68歳。士官学校を経て陸軍将校となり、10年に軍統合参謀長、11年に国軍トップの総司令官に就任した。国際社会の圧力でミャンマーは16年にアウン・サン・スー・チー率いる民主的な政府が誕生するが、実際には政府はミン・アウン・フライン率いる軍部の了解の範囲内での政治しか許されなかった。それでも民主派勢力が勢いを増したことで、21年にクーデターを起こし、以後、軍事政権を率いている。
ミン・アウン・フラインはミャンマー軍による反政府ゲリラ支配地域への過酷な弾圧を指揮しているが、日本政府とは良好な関係を続けている。これまで何度も訪日しており、日本の首相や防衛相と会談している。なお、非人道的なミャンマー国軍と日本防衛省の交流は緊密で、長年、防衛省はミャンマー国軍将校を受け入れて教育してきた。
24月11月、ミン・アウン・フラインは、西部のバングラデシュとの国境地帯に住むイスラム教徒のロヒンギャ人を迫害したとして国際刑事裁判所にて逮捕状が請求された。しかし、日本外務省では、ミャンマー軍事政権がその存在を認めていない「ロヒンギャ」という言葉はタブーとされている。西側主要国が軍事政権を非難するのに対し、日本政府の親ミャンマー政府ぶりは突出していると言えよう。
他方、今回の大地震に際し、反政府ゲリラの最大勢力である民主派勢力は、震災救助活動のため、一時的な停戦を宣言している。旧・民主派政府組織「国民統一政府」(NUG)の軍事部門「国民防衛隊」(PDF)が、3月30日から2週間の軍事作戦の停止を発表したのだ。
このNUGを率いるのが、ドゥワ・ラシ・ラー大統領代行だ。彼は少数民族のカチン人で、1950年生まれの74歳。教師、検察官、法務官などを経て民主派政治家に転身。カチン全国諮問評議会の議長となり、21年の軍部クーデターの後、NUGの大統領代行に就任した。ウィンミン大統領が軍事政権に拘束されているため、事実上、NUGのトップとなっている。そして、ドゥワ・ラシ・ラー大統領代行が軍事政権に対する武装闘争を宣言したことで、強力な反政府ゲリラが誕生したのだ。
そのNUGの軍事部門であるPDFを率いるのが、イー・モン国防相である。彼は1967年生まれの57歳。医学生だった88年に民主化運動に参加して逮捕され、7年間収監される。釈放後、環境活動家として活動を開始。15年の総選挙で国会議員に当選し、民主派政治家として活動するが、21年のクーデターの後、NUGの国防相に任命された。現在、10万人以上とみられる反政府ゲリラであるPDFの事実上のトップに任命されている。
PDFはミャンマー最大の反政府ゲリラだが、88年の民主化闘争時からの反政府ゲリラである「全ビルマ学生民主戦線」や、有力な少数民族ゲリラである「カレン民族同盟」「カチン独立機構」「カレンニー民族進歩党」「チン民族戦線」などと同盟関係にあり、広範囲な影響力を保持している。武装闘争歴はこうした各派の指揮官たちのほうが長いが、最大のゲリラ組織を率いる司令官として、現在はドゥワ・ラシ・ラー大統領代行とイー・モン国防相の影響力がきわめて大きい。
ウクライナ戦争やガザ紛争などに比べ、東南アジアの小国で起きている地味なミャンマー内戦は国際社会でもあまり注目されていないが、軍事政権と民主派ゲリラの闘いとそれに付随する軍事政権による民間人の殺戮、あるいはロヒンギャ人などの少数派への弾圧など、人道危機の根は深い。
黒井文太郎(くろい・ぶんたろう)1963年福島県生まれ。大学卒業後、講談社、月刊「軍事研究」特約記者、「ワールドインテリジェンス」編集長を経て軍事ジャーナリストに。近著は「工作・謀略の国際政治」(ワニブックス)